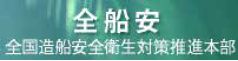サステナビリティ

造船が創る、
豊かな未来。
日本の造船業は、江戸時代末期の1853年頃から、人々の暮らしや産業を支える船舶を建造してまいりました。国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向け、船造りを通じて社会課題の解決、社会貢献活動に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現を目指していきます。
社会課題①
低炭素社会の構築
大量に運べて環境に
やさしい海運
船による大量輸送を行う海運は、トラックや飛行機などの輸送手段と比べて、輸送効率面でとても優れています。
貨物1トンを1マイル輸送するのに排出されるCO2

出典: IMO 「Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020」、IEA「Energy Technology Perspectives (ETP) 2020)」、国土交通省「航空輸送統計年報(2019)」からの計算を基に作成
社会課題②
自然共生社会の構築
環境汚染・生態系への
影響の最小化
GHG削減及び将来のカーボンニュートラルに向け、性能改善や省エネ装置の開発による燃料消費量削減に加え、LNG、アンモニア、水素などの環境にやさしい燃料で航行する船舶の開発が進められています。また、エンジン排ガスに含まれるNOxやSOxについても、国際ルールの規制を満たすべく舶用メーカーと取り組みを進めています。生態系への影響の最小化についても、フジツボなどの海洋生物が船に張り付きにくくなる塗料の使用や、バラスト水(海水)に含まれる微生物等が違う海域で放水されることがないよう対策をしています。

社会課題③
循環型社会の構築
3Rを通じた資源循環の最大化
船の多くは90%以上が鉄を原料としています。船の寿命は約30年と言われ、最終的には解撤されて、電炉によって再び鉄に戻されるため、資源の循環性が高い製品であると言えます。
社会課題④
技術伝承
造船技術者の育成
当会は、造船業における若手技術者の技術力向上を図ることを目的とした「造船技術者 社会人教育」事業や、大学において将来の造船技術の開発・挑戦を実践する人材への資金援助事業(造船学術研究推進機構:REDAS)などを行っており、造船技術者育成に努めています。


SDG’sの達成に貢献
日本の造船業では、脱炭素化の推進や海洋環境の保護といった
環境保護に向けた取り組みはもとより、より安全な海洋輸送を実現するための技術革新や経済成長を支える
産業基盤の構築など、持続可能な未来を築くための様々な取り組みを行っています。


-
油など
海洋汚染対策
●油流出の未然防止、被害の最小化
●汚水や廃棄物の処理 -
Sox、Nox、
PM+等大気汚染対策
●エンジンの改善
●良質燃料への切り替え -
温室効果ガス
地球温暖化
対策●燃費改善
-
廃船、有害物質
(船の解体/
リサイクル時)次元循環への
対策●廃船の再資源化
●解体時の環境・
安全対策の徹底 -
外来生物
(パラスト水に
含まれる)生物多様性
への配慮●外来生物の越境移動の防止






「統計データ」「安全衛生関係資料」は、
一部の資料を除き会員様のみに公開しております。